
革新センシング技術創成分野リーダー
澤田 和明
集積回路技術とセンサ技術を融合した種々のスマートセンサを研究開発しています。新しい原理のセンサによる高感度化・高機能化と、そのセンサの優位性を発揮するための信号処理を一体化し、特に、バイオ関連技術と集積回路技術を融合した”インテリジェントバイオチップ”関連の研究を進めています。

澤田 和明
集積回路技術とセンサ技術を融合した種々のスマートセンサを研究開発しています。新しい原理のセンサによる高感度化・高機能化と、そのセンサの優位性を発揮するための信号処理を一体化し、特に、バイオ関連技術と集積回路技術を融合した”インテリジェントバイオチップ”関連の研究を進めています。

沼野 利佳
近年研究の分野も境界がなくなり、様々な領域の研究者があつまって一緒に探求することが必要です。神経科学の分野も同様で、このエレクトロニクス先端融合研究所は、私の遺伝子工学や実験動物を用いた生理学研究の知識や技術と、センサー技術や情報科学、薬理学など多彩なアプローチも駆使して、生命現象の奥に流れている真理を突き止めるとともに、新しい技術を社会実装にもつなげてゆきたいです。

中内 茂樹
私たちは普段、何の苦労も感じることなく物を見て、理解し、行動しています。こうした「視覚」を支えている脳機能や仕組みを解明するとともに、そうした基礎研究に裏打ちされた新しい視覚情報処理技術を開発しています。

柴富 一孝
新たな高機能光学活性触媒の開発、キラルハロゲン化合物の不斉合成、炭素-ハロゲン結合の開裂反応、キラル医農薬品の高率合成を主なテーマとして、従来達成困難であった反応や斬新な発想に基づくユニークな反応の開発にチャレンジしています。

松田 厚範
ゾル-ゲル法、メカノケミカル法、交互積層法、電気泳動堆積法、陽極酸化法などによる次世代エネルギーデバイスに関する以下の機能性材料の作製と応用について研究を行っています。
1.プロトン伝導性固体材料の作製とイオニクス素子への応用
2.次世代燃料電池用新規ハイブリッド電解質材料の開発
3.硫化物系全固体リチウムイオン二次電池の開発

高山 弘太郎
植物工場などの環境制御型植物生産を対象として、植物生体情報に基づいた高度な栽培・労務管理を実現するための植物診断技術(クロロフィル蛍光画像計測、匂い成分計測、光合成蒸散計測)の開発と社会実装を行っています。さらに,IRES²で開発されるセンサ・MEMSデバイスを活用した先端的農業生産技術を開発します。
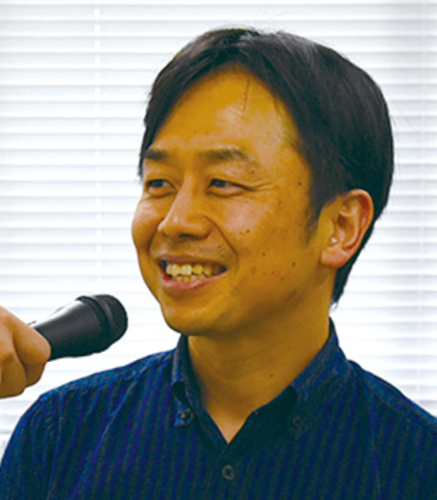
河野 剛士
私たちの脳は複雑ですが魅力的でもあります。この脳情報を正確に捉えるために脳と直接接続するエレクトロニクス技術の研究を行っています。これまでに,半導体シリコン成長法と集積回路技術を用いた世界で最も細いニードル電極の製作、その計測技術の高品質化、またマウスやサル等の大脳皮質からニューロン計測に成功してきました。今後はさらに世の中が驚くような脳や生体と繋がるエレクトロニクスの研究にチャレンジしていきます。

永井 萌土
マイクロ・ナノ領域の作業のスケールアップに取り組んでいます。特に細胞治療や創薬では、単一細胞を大量に加工することが求められています。マイクロ・ナノデバイス、メカトロニクス、情報科学の力を総合し、ハイスループットな細胞加工を実現します。

松井 淑恵
音声から相手の意図を読み取り、環境音で状況を判断し、音楽に合わせて体を動かす、このような音に対する反応が、聴覚への入力からどのようにして起きるかを解き明かすことを目指しています。また、さまざまな聴力を考慮した「音のユニバーサルデザイン」にも取り組んでいます。

鯉田 孝和
視覚認知を司る脳の働きを理解するためヒトを対象とした心理実験とともに、IRES²-3ライフサイエンスラボにて動物(マカクザル・マウス)の行動とニューロン活動を計測しています。また革新的な電極技術を開発しています。

野田 俊彦
IRES²-2のLSI工場を活用し,CMOS/MEMS技術に基づくマルチモーダルセンサの研究を行っています。本学で開発されたイオンイメージング技術やかおりセンシング技術とディープラーニング技術を融合して,バイオメディカル分野,農業分野,環境計測分野への展開を進めています。

有吉 誠一郎
テラヘルツ光は電波と可視光それぞれの技術的進展とは対照的に“光のフロンティア”と呼ばれています。本研究室では、低温・高温超伝導体を用いたテラヘルツ光検出デバイスや2次元分光技術の開発、およびこれらを駆使して、ポリマーの分光学的研究や新たな応用分野の開拓を目指しています。応用化学・生命工学系を兼務しています。

Mohammad Shehata
本研究ではヒトが何かに没頭しているときに脳内で何が起きているのか調べています。 これまでの研究で2つの脳の状態が存在することが解ってきました。 一つは難しさを感じることなく超絶テクニックを発揮でき楽しさを感じる「フロー状態」、もう一つは失敗に対する不安で身動きできない「チョーキング状態」です。 様々なヒトと連携する社会的条件下では、スポーツチームや音楽団体のように、チームフローが発生します。 こうした現象に対する認知神経科学的理解を基盤として、フローを強化し、チョーキングを防ぐニューロフィードバック技術を開発しています。

増沢 広朗
ロボットの環境認識に関する研究・開発を行なっております。特に、農業用ロボットのための認識に関する研究をおこなっております。農場はロボットが活躍するには難しい場所ですが、農業分野のロボット応用は必要不可欠と考えています。

辻 正芳
戦略マネジメント部門において研究力の高度化と社会実装を推進します。国内稀有の一気通貫半導体プロセス設備を有する環境を生かし、研究成果の拡大及び社会貢献を図るとともに、産官学の技術者・研究者の人的ネットワークを構築するハブとしての機能を高めていきます。

田中 三郎
高温超伝導デバイスの一つ、超高感度磁気センサSQUID (Superconducting Quantum Interference Device)の高性能化を中心とした研究を行っており、SQUIDの非破壊検査、バイオセンシング、超低磁場NMR・MR等への応用展開をしています。

堀内 浩
CMOS技術に基づくバイオケミカルイメージセンサと2光子イメージングを駆使して、生体脳における細胞外環境と神経回路活動の相互作用を理解し、複雑な脳機能や病態メカニズムを解明します。また、生体適用によって得られた基礎データをチームに提供し、センサ開発の実用性の向上に貢献します。

飛沢 健
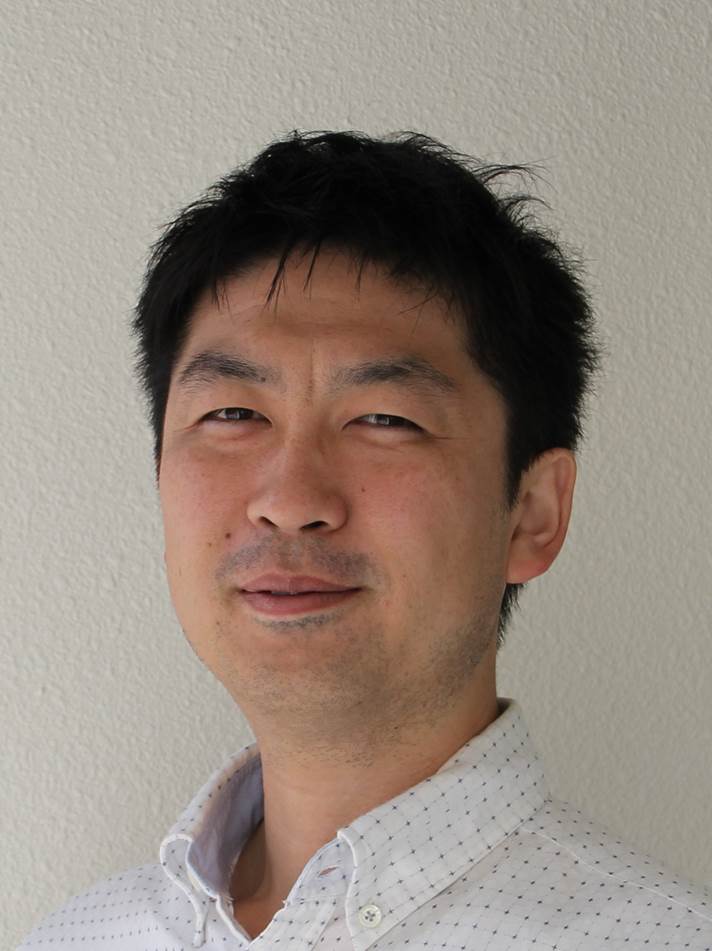
赤井 大輔
IRES棟、VBL棟の管理、施設・設備マネージメント担当。LSI工場を活用した集積回路、センサ・MEMS試作に関して、技術相談から試作・装置利用までワンストップサービスを提供しています。
坂井 悦子
大屋 翔
野田 佳子
堀尾 智子
中村 祐子
田村 三恵
鈴木 美和